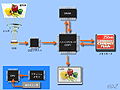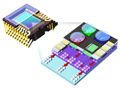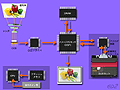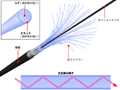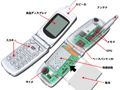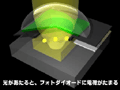| - 啓林館 情報C - |
第1章 情報のディジタル表現と情報機器
|
2103
 | 【教師向けコメント】 アナログ式のLPレコードとデジタル式のCDの情報の記録の仕方の違いについて学習できます。LPレコードは直接針が触れるために、情報が磨耗してしまうことにも触れるといいでしょう。実際に音をどのようにディジタル化するかは2108を参照してください。 |
【生徒向け】 アナログメディアであるLPレコードとディジタルメディアであるCDのデータの記録方法を比べてみましょう。LPレコードは記録面に直接針が触れるのでデータが磨耗してしまうことも理解しましょう。 |
1305-1
 | 【教師向けコメント】 フラッベッド型のイメージスキャナの構造を示すときに利用することが出来ます。この際、主な部分の説明を簡単にすると尚いいと思います。 |
【生徒向け】 フラットベッド型のイメージスキャナの主な構造を知ることが出来ます。原稿台の上にスキャンしたい方を下にして置き、キャリッジで読み取ります。 |
1306-1
 | 【教師向けコメント】 どのようにスキャナを使ったらいいのかを示したいときに利用するといいでしょう。 |
【生徒向け】 スキャナを使うときの注意事項を知りましょう。説明にあるように、原稿全体をスキャンするのではなく、低解像度で原稿をスキャンし、範囲を指定して必要な部分だけを高解像度でスキャンするようにすると時間の短縮になり、よいですよ。 |
1307-1
 | 【教師向けコメント】 ディジタルカメラの構造を示す時に利用できます。その際、各部の簡単な説明を加えるといいでしょう。 |
【生徒向け】 ディジタルカメラの構造がどうなっているかみてみましょう。普通のカメラの仕組みを調べ、どこが違うか考えてみましょう。 |
1307-2
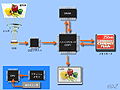 | 【教師向けコメント】 1307-1で紹介された各部分がどのような役割をしているかの説明をする際に利用することが出来ます。ディジタルカメラで撮影してからメモリカードに書き込まれるまでの過程がわかります。 |
【生徒向け】 1307-1で示されていた各部分は、どのような役割を果たすのでしょうか。全体的な流れを追ってみましょう。 |
1309
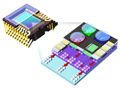 | 【教師向けコメント】 CCDの構成、特に受光部の細かい構成を示すことができます。これを使用する際には、各部の簡単な説明を加える必要があります。 |
【生徒向け】 ディジタルカメラやスキャナのキャリッジで出てきた「CCD」の内部構造を見ることができます。専門的なので眺める程度でよいでしょう。 |
1309-1
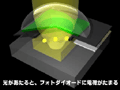 | 【教師向けコメント】 CCDに光を当ててからどのように画像データが得られるのかの流れを示したいときに利用するとよいでしょう。フォトダイオードについての説明がされてませんので、付け加えておくとよいかもしれません。また、前知識として、画像がRGBで示されることを教えておく必要があります。 |
【生徒向け】 CCDに光を当ててからどのように画像データを得ることが出来るのか見てみましょう。専門的な話なので、細かな数字は気にせず、全体的な流れをつかむようにするとよいでしょう。 |
1310-1
 | 【教師向けコメント】 ディジタルビデオカメラの構成を示したい時に利用できます。その際、各部の簡単な説明を加えるといいでしょう。 |
【生徒向け】 ディジタルビデオカメラの構造はどうなっているのかみてみましょう。ディジタルカメラとの、部品の違いをみてみましょう。 |
1310-2
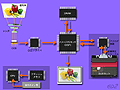 | 【教師向けコメント】 "ディジタルビデオカメラで撮影してから、DVカセットに画像を記録する過程を示すことが出来ます。
この際、ディジタルビデオカメラと相違点を示すといいでしょう。" |
【生徒向け】 1310-1で示されていた各部分は、どのような役割を果たすのでしょうか。全体的な流れを追ってみましょう。また、ディジタルカメラと比べて、同じ点・異なっている点を考えてみましょう。 |
1704
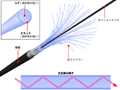 | 【教師向けコメント】 光ケーブルは、極端に曲がると光信号が送ることができなくなるので、テンションメンバを入れることでゆるやかに曲がるようになっています。実物の光ケーブルや光ファイバを見せて説明することで理解しやすくなります。 |
【生徒向け】 1本の光ケーブルには、複数の光ファイバを束ねられています。 |
1705-1
 | 【教師向けコメント】 モデム・ADSL・光ファイバーの通信速度の異なる手段の、画像の転送の速度の違いを学習できます。 |
【生徒向け】 象が歩く映像を使って、モデムとADSLと光ファイバで表示されるまでの速度を体験的に見ることができるように説明しています。モデムは56Kbps、ADSLは1.5〜8M、光ファイバは10〜100Mの設定なので、正確な時間ではなく、体感的な速度を体験できるような映像になっています。 |
4101
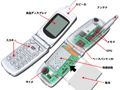 | 【教師向けコメント】 携帯電話の構造から、信号の流れをCPU中心におさえておくと良いでしょう。 |
【生徒向け】 携帯の中にもCPUが活躍しています。ここでは、信号の流れをつかむことが大切です。 |
4102
 | 【教師向けコメント】 セル(通信可能範囲)と基地局、そして携帯電話の役割に注目した上で、携帯電話による電波の受発信のしくみを概観しておくことが大切です。 |
【生徒向け】 基地局の役割に注目しましょう。具体的には、携帯電話が電波を発信してから相手の位置を特定して呼び出す方法に注目しましょう。 |