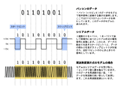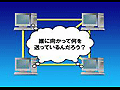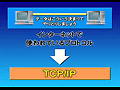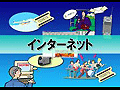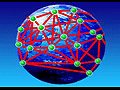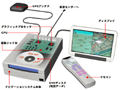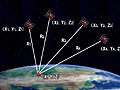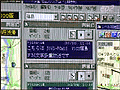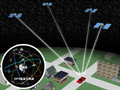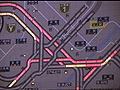| - 第一学習社 情報B - |
第4章 情報社会と情報技術
|
1702
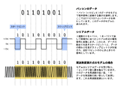 | 【教師向けコメント】 周波数変調の説明は、ディジタル信号をアナログ信号に変換するわかりやすい例です。実際に波形を見せたり音を出したりするとより理解がしやすくなります。 |
【生徒向け】 データを転送するときには、回線の状況によりそのまま伝わるとは限りません。そこで、データの始まりと終わりに印をつけることで、正しくデータをうけとっているかどうかを判断します。 |
1705-1
 | 【教師向けコメント】 モデム・ADSL・光ファイバーの通信速度の異なる手段の、画像の転送の速度の違いを学習できます。 |
【生徒向け】 象が歩く映像を使って、モデムとADSLと光ファイバで表示されるまでの速度を体験的に見ることができるように説明しています。モデムは56Kbps、ADSLは1.5〜8M、光ファイバは10〜100Mの設定なので、正確な時間ではなく、体感的な速度を体験できるような映像になっています。 |
1707-1
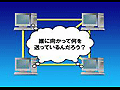 | 【教師向けコメント】 プロトコルの概念や役割を、電話を例にして、学習することができます。 |
【生徒向け】 コンピュータを線でつないだだけでは情報のやりとりができません。ネットワークでデータをやりとりするときの決まりごとをプロトコル(通信規約)といいます。 |
1707-2
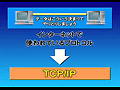 | 【教師向けコメント】 パケットの必要性や構成について学習することができます。 |
【生徒向け】 ネットワークでのデータは「パケット(小包)」という単位でやりとりされます。また、パケットが無事に届くためには「ヘッダ」に書き込まれた情報が重要になります。 |
1707-3
 | 【教師向けコメント】 ネットワークのトラブルに対処するためには、こうしたプロトコルの階層構造に対する理解が必要となります。内容的に難しいと思われる場合は、1707-3-01および02の静止画を使って、説明するとよいでしょう。 |
【生徒向け】 プロトコルは1つではなく、層を作って、それぞれの役割をはたしています。ネットワークがうまくつながらないという場合は、どの層での問題なのかをはっきりさせることが第一歩です。 |
1707-4
 | 【教師向けコメント】 UDP上のアプリケーション層で使うプロトコルは主にネットワーク管理に使われています。こうした管理の側面を説明する場合には、この部分がかかせません。 |
【生徒向け】 TCPは、トランスポート層のプロトコルです。また、アプリケーション層では具体的にどのようなプロトコルが使われているか調べてみましょう。 |
1708-1
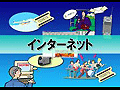 | 【教師向けコメント】 インターネットの成り立ちを学習することができます。 |
【生徒向け】 インターネットの歴史はまだ浅く、はじまりはアメリカのARPNETといわれています。最初は軍事から学術、そして一般のネットワークへと広がっていきました。 |
1708-2
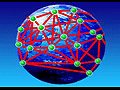 | 【教師向けコメント】 インターネットの概念について、しくみ、信頼性、利点について学習できます。 |
【生徒向け】 TCP/IPを利用できる機器であれば接続が可能な開かれたネットワークが、インターネットです。インターネットに接続できる機器には、コンピュータ以外にどんなものがあるか、あげてみましょう。 |
4107
 | 【教師向けコメント】 エアコンによる空調制御について内容がかなり専門的になり過ぎているため、まずは、センサーとモータの連携からいかにして空気中の温度が制御されているのかをつかむ必要があります。おおまか過ぎる構造図ですが、素材番号4106(エアコンの構造)を必要に応じて参照することでイメージがつかみやすくなることでしょう。 |
【生徒向け】 センサーとモータの連携がイメージできればよいでしょう。 |
4105
 | 【教師向けコメント】 自動車で活躍しているコンピュータについて、図で示されている構造面と機能面との対応をさせておくことが大切です。 |
【生徒向け】 自動車で活躍しているコンピュータについて、機能面からあげながら図(構造面から示されているもの)と比べてみましょう。 |
4103
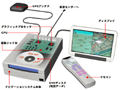 | 【教師向けコメント】 目的ルートの検索方法、位置情報の補正方法について概観しておく必要があります。その際、GPSの知識、CPUのはたらきに注目しておくことが大切です。 |
【生徒向け】 CPUとDVDのはたらきに注目しながら、位置の特定方法を調べてみましょう。 |
4104
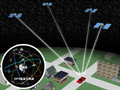 | 【教師向けコメント】 地球を周回するGPS衛星は、現在の衛星の位置と正確な現在時刻の情報を電波に乗せて送信していますが、それが、以下の2点にどのように生かされているかを概観しておくことが大切です。
(1)GPS衛星と現在位置との距離の計算。
(2)衛星からの距離と位置情報からの現在位置の計算。 |
【生徒向け】 GPS衛星が、現在位置を計算するために行っている方法に注目して調べてみましょう。調べた方法について、生徒相互に発表し合う展開が望まれます。 |
4202-1-1
 | 【教師向けコメント】 有料道路の料金所に設置した道路側アンテナと車載器の間で行われる「無線通信」のしくみについて、料金情報をやり取りする方法としておさえておくことが大切です。 |
【生徒向け】 有料道路の料金所を通過する車の料金情報をやり取りするためのくふうについて考えてみましょう。これを「無線通信」に発展させるとより学習成果が期待できます。 |
4202-2-1
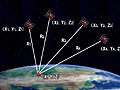 | 【教師向けコメント】 コンピュータを駆使して位置を測定する方法について考えることが大切です。 |
【生徒向け】 位置を測定するためには、正確な時刻情報や軌道情報などを送り続けることと、この情報を利用して自分の位置を計算することが必要です。このとき、コンピュータがいかなる活躍をしているかを考えてみましょう。 |
4202-2-2
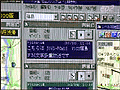 | 【教師向けコメント】 VICSとは何か。そして、何ができるのかを機能別に概観しておく必要があります。その際、そこで活躍するコンピュータの役割を押さえておくことが大切です。 |
【生徒向け】 VICSが提供するサービスには何があるかを調べてみましょう。また、そこで活躍するコンピュータのはたらきをあげてみましょう。 |
4202-2-3
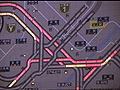 | 【教師向けコメント】 全国の道路交通情報を収集するシステムにはどのようなものがあるのかを概観する必要があります。その際のポイントとして、
(1)全国をオンラインで結ぶ体制、
(2)日本道路交通情報センターとVICSセンターとの情報のやりとり方法、
(3)コンピュータの利用方法
があります。ここでは、(1)について考えておくと良いでしょう。 |
【生徒向け】 全国の道路交通情報を収集する際、全国をオンラインで結ぶ体制について考えてみましょう。 |